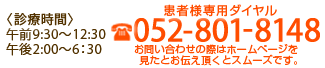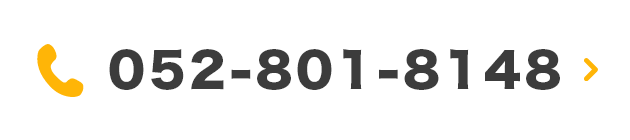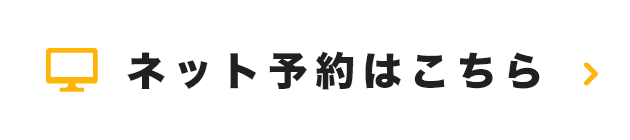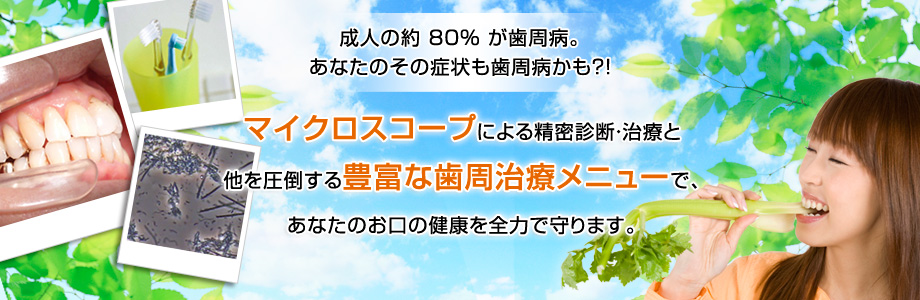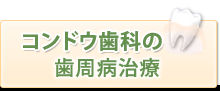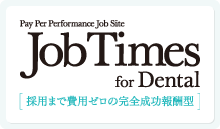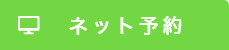-
2024年07月15日 月曜日
歯の間に物が詰まる
歯の間に物が詰まる。食片圧入という状態があります。
食片圧入する理由
1. 歯の間に隙間
歯の間の隙間が中途半端だと物が詰まりやすくなります。いっそ空きすぎている方が、詰まらなくなります。
2. 歯周病
ものを噛み合わせる時、動揺している歯が微妙に動くために歯の間に物が入ってしまいます。
3. 咬み合わせ
上下の歯の咬み合わせがうまくいっていない時です。隣の歯との段差があり、咬み合わせた時に食物がはさまってしまう。
4. 食物の形態
線維性の食べ物はその形状から間に挟まりやすくなります。食片圧入に対する対処
食片圧入する原因を確かめ、それに対応した対処をします。
歯の形態修正をしたり、場合によっては連結冠という方法を取ります。 -
2024年06月24日 月曜日
歯周病原菌の種類
歯周病の初発原因となる歯周病原菌は1種類の菌だけではなく、複数の細菌が関与しています。
口の中には300~400種類の菌が存在しますが、そのうち歯周病に関与しているのは15種類程度(あるいはそれ以上)の菌です。歯周病菌の種類
慢性的な歯周病では、ジンジバリス、デンティコラ、フォーサイセンシスの3種類の菌が多く(60~70%)見られます。
これらのレッドコンプレックスと呼ばれる3種類の菌は、歯周病に深刻な影響を与えます。
歯肉に炎症を起こして歯周ポケットを形成し、歯周病が進行していきます。やがて歯槽骨が失われてしまいます。
アクチノバチルスAA菌は、若年時に歯周病を重症化させます。
インターメディア菌は、女性ホルモンによって発育し、思春期や妊娠時に増加して歯周病を引き起こします。予防策
プラーク1mg中には1億個以上の細菌が含まれます。
従って、歯周病予防には、プラークを出来るだけ減らすことが大事になります。 -
2024年06月17日 月曜日
歯周病の原因となるプラークとは
歯周病の初発原因は、プラーク(歯垢)の中にある歯周病原菌です。
プラークとは
歯面に付着している白色から黄白色をした粘着性をした付着物です。
バイオフィルムと呼ばれる細菌の塊です。
プラーク中の細菌は、約600種類で1mg中に1~2億個存在しています。
プラークは歯肉に炎症を引き起こす最も重要に因子です。歯肉炎や歯周炎は、プラークが存在すると生じます。
歯にしっかり付着していて、うがいや薬剤などで落とせないので、機械的に歯ブラシで除去します。プラーク増加因子
局所の清掃を不良にしてプラークを増加させたり、落としにくくしたりする因子のことです。
プラークリテンションファクターと呼ばれるものです。
歯石、歯並びの悪さ、口呼吸、歯冠の形態不良、歯肉形態不良、小帯の異常、不適合修復物、食片圧入などがあります。
また、歯周病が進行して歯周ポケットが深くなると清掃がより困難となり、歯根露出して歯間部に隙間があるとなかなかプラークが落とせなくなります。 -
2024年06月10日 月曜日
歯周病による口臭
口臭が起こる原因には、いくつかあります。歯周病もその一つです。
口臭の原因
1. お口の中に原因がある。
歯周ポケットの中に細菌が増え、硫化水素やメチルカプタンという口臭の原因となる物質が産生されます。
歯周からの排膿、食べかすが詰まる、舌苔が溜まるなども原因です。
2.消化器官、呼吸器官などの疾病
胃潰瘍、扁桃炎、糖尿病などの疾病です。
3.食べ物
ニンニク、ネギなどの食べ物です。
4.生理的口臭
朝起きた直後、ホルモンのバランスが崩れるなどです。口臭対策
お口の中を清潔に保つことが大事です。
歯磨きや舌の清掃、うがいにより口臭を予防しましょう。
歯周病は普段からかかりつけ歯科医院でチェックしてもらいましょう。
鼻疾患などで口呼吸しているとお口の乾燥により、口臭が増大するので、治療を受けておきましょう。 -
2024年05月27日 月曜日
歯を支えている支持が弱くなり、と歯周病
咬耗とは、咬み合わせにより歯が摩耗してすり減った状態のことです。歯周病と関係があるのかをお話しします。
咬耗の原因は
咬耗する原因には、
1. 過度にその歯だけ使っている。
2. 歯ぎしりや食いしばりなど、強い力が歯にかかっている。
3. 歯周病で歯が挺出(炎症で歯が浮いて強く当たるなど)して、そのためにその歯が強く当たるようになった。
などです。歯周病との関係
前述のように、歯周病の炎症で歯が浮き上がり、その歯が強く噛み合わさってしまう。
歯周病により歯を支えている支持が弱くなり、病的な歯の移動が起こっている場合などは、何本かの歯が影響を受けます。
最初にその歯が噛み合わさるという早期接触が起こり、咬合性外傷という状態になります。どうすればイイの?
歯周病はスケーリングなどの治療だけではなく、咬み合わせのチェックも行ってもらいましょう。
perio Blogブログ新着情報
カテゴリ一覧
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
最近のブログ記事
月別アーカイブ
-
2024年 (25)
-
2023年 (52)
-
2022年 (52)
-
2021年 (52)
-
2020年 (52)
-
2019年 (52)
-
2018年 (53)
-
2017年 (51)
-
2016年 (52)
-
2015年 (50)
-
2014年 (52)
-
2013年 (52)
-
2012年 (57)
-
2011年 (49)